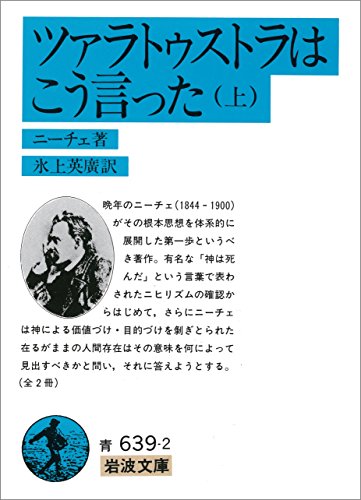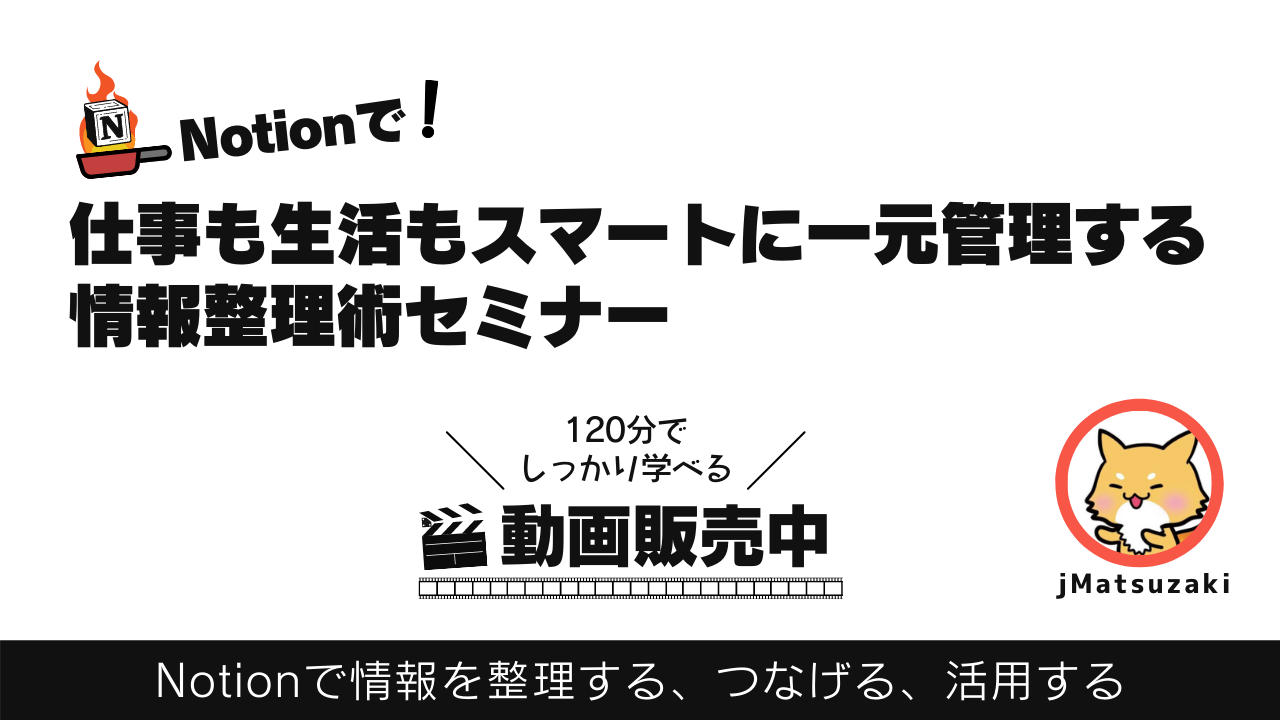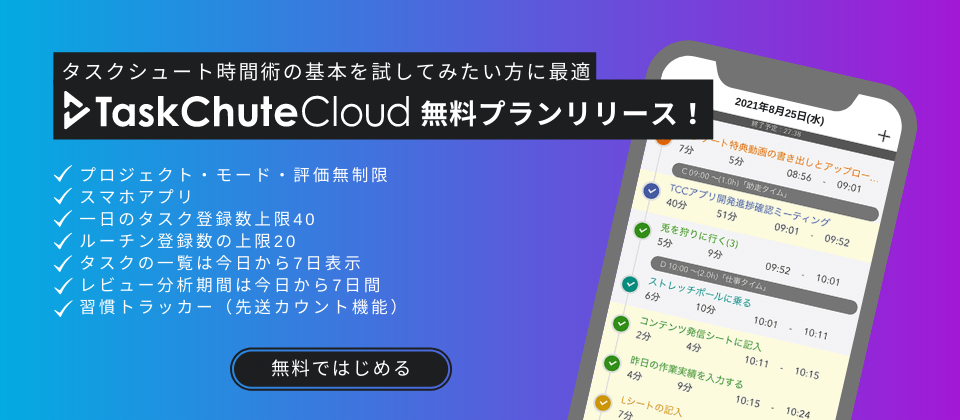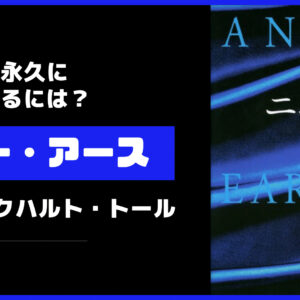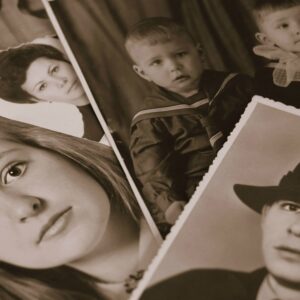私の愛しいアップルパイへ
15歳の頃に出会って以来、生きる指針として度々参照している本の1つにフリードリヒ・ニーチェ著「ツァラトゥストラはこう言った」(原題:Also sprach Zarathustra)があります。ドイツを代表する哲人であるご存知ニーチェが1880年代、今から100年以上も前に書いたニーチェの代表作ですが、現代にも通ずる、というよりも現代にこそ必要な思想が詰まっていて、大変影響を受けました。

後の1896年に、同じくドイツ出身の音楽家であるリヒャルト・シュトラウスが同名の交響曲を作曲したことでも有名です。この曲も現代でも至る所で日常的に耳にする名曲です。
個人的な思い出でいえば、高校をサボって舐めるようにこの本を読んでいたのを、今でもよく思い出します。当時は詩の勉強として読み始めたのですが、この本にはすっかり人生を変えられてしまいました。
本書は分厚い一冊なのでその内容を全て正確に紹介するのは難しいので、今日は本書の中心的なテーマを簡単にあなたにも紹介したいと思い今日は筆を取った次第であります。
▼なお、動画による解説もありますので、ながら聴きなどこちらをご覧ください。
それでは早速本題に入っていきましょう。
フリードリヒ・ニーチェ著「ツァラトゥストラはこう言った」とは?
本書「ツァラトゥストラはこう言った」(ツァラトゥストラはこう語った、ツァラトゥストラかく語りき、ともいう)はドイツの哲人であるフリードリヒ・ニーチェが39歳の時、1883年〜1884年にかけて執筆された彼の代表作です。ニーチェ哲学の集大成といえる一冊となっています。
本書はニーチェが大きな失恋を経験した直後で、かつ師ともいえるドイツの哲人アルトゥル・ショーペンハウアーやかねてより認め合っていた伝説的な音楽家リヒャルト・ワーグナーとの決別、また病の悪化による療養生活の中で、孤独に執筆に没頭して完成させました。
かような絶望の中で、ニーチェは人々が人生をいかにして生きるかについて大胆なインスピレーションから真理を追求し、ついに回答を見出したのでした。それを世界で初めて善悪二元論を説き、最も善悪の矛盾に詳しく、誠実に真理を探求したであろうとニーチェが考えたゾロアスター教の開祖の名に乗せ(ツァラトゥストラはゾロアスターのドイツ語読み)、自身の哲学を物語形式で語らせたのでした。
当時は本書を印刷してくれる出版社が見つからず、初版はたったの40部だったそうです。ニーチェは本書が売れる見込みも全くない中で、ひたすら自分と対話し、情熱をぶつけ凝縮させたBurning!な一冊が本作なのです。
本書を書き上げた後から病が悪化していき、晩年ニーチェは狂人と化していくので、本書はニーチェの集大成であり、代表作であり、全盛期の一冊だといえるでしょう。
「ツァラトゥストラはこう言った」要約まとめ
本書は膨大な文量がある一冊なので、簡単にまとめられるものではないのですが、本書の根幹をなす3つの概念を紐解きながら要約してみましょう。
19世紀末に起きた「神の死」とは?
「神は死んだ」
これはニーチェの最も有名なセリフの1つでしょう。このセリフは「ツァラトゥストラはこう言った」の冒頭でツァラトゥストラが語るものです。セリフだけ一人歩きしがちなこの一説にはニーチェ哲学の重要な前提条件が詰まっています。
このセリフ、実はこの後こう続きます。
「神は死んだ。人間への同情のために死んだのだ。」
19世紀末というのは、ヨーロッパ各国で市民革命が起こり千年以上続いた体制が崩壊しました。313年に古代ローマでキリスト教が公認されて以来続いたキリスト教社会がついに崩壊した頃です。並行して産業革命が起こり、イギリスが「世界の工場」として君臨するなど、技術的にも大転換の起こった時期でした。
そのような時代背景にあって人々の死生観が大きく変わっていき、人生に新しい意味が必要となる時代でした。これは現代の状況にも通ずるものがあります。
そんな中、ニーチェは「神は死んだ」という言葉の中で、キリスト教的教義から生まれる人々の死生観を痛烈に批判しました。人は誰もが罪人であり、天に召された暁には現世で詰んだ徳の量によって罪が軽くなり、罪が軽ければ天国に行き、重ければ地獄に落ちるという目的論的原理を批判したのです。
このような目的論的原理の基で、宗教的な教義にすがって救いを求める生き方。ときには宗教的な教義に基づくことで、目先の生活の保証や快適さを得られれば満足とする思考停止にニーチェは我慢ならなかったのです。かような状況をニーチェは神による人間への同情だと表現し、キリスト教を始めとする当時の思想や道徳のスタンダードであった宗教的教義を「奴隷道徳」だと厳しく非難しました。
しかし、神を殺した代償として人は生きる意味を失ってしまいます。そこでツァラトゥストラが提示したのは全く新しい生きる意味だったのです。
誰もが目指すべき理想像「超人」とは?
「神は死んだ」と宣言したツァラストラが前半部分で説くのは「超人」についてです。
これは、将来死んだ時に天国へ行けるために現世で徳を積むという考え方と真逆を行く概念です。ニーチェはそのような目的原理を完全に否定し、人生に画一的な生きる意味などはなく、人生にあるのは自らの力を発揮したいと欲する「力への意志」であると考えました。
しばしば超人の概念はダーウィンの進化論における生物学的な意味での超人を意味すると誤解されがちで、20世紀にナチスドイツが政治的目的で積極的にこの用語を利用したことで誤解に拍車をかけましたが、ニーチェが説いた超人はもっと個人的で意志と生き方に関連するものです。
自らの力への意志に従い、社会通念から生まれる善悪に左右されることなく、ただひたすら自分自身を超えて「自己超克」し続けること。この連続によって辿り着けるのが「超人」だと説いたのです。
これは19世紀当時では個人的思想に留まらず、社会通念でもあり強大な政治的な権力をも持つ当時の支配的な思想であったキリスト教の基本的な教義と真逆をいきます。人の視点を未来から現在へと移していく当時としては極めて画期的な考え方でした。
まったく新しい生きる指針「永劫回帰」
超人の思想を経て、後半で中心的に語られるのがニーチェ哲学の到達点ともいえる「永劫回帰」です。これはしばしば輪廻転生と混同されることがありますが、考え方も目的も意図もまったく違います。
永劫回帰とは端的に言えば、「今日という日が未来永劫、無限に繰り返されるとしても、それでもなお生を肯定する」という思想です。
ニーチェは超人の考え方によって人生の目的論的原理を完全に否定し、人生に画一的なゴールも目的も存在しないと説きました。そこで必然的に生じる問いは、「ならば、なぜ人は生きるのか?」という問いでしょう。さもなくばニヒリズムに陥りかねません。この問いに対するニーチェの回答が永劫回帰となります。
永劫回帰には輪廻転生のように生まれ変わりや来世という考え方は存在しません。似ているどころか真逆をいくもので、前世や来世といった考え方をニーチェは真っ向から否定して、今の自分が無限に繰り返されるという考え方をベースとしています。
明確なゴールも目的地も持たない人生において、ある面では単なるニヒリズムともとられかねないこの思想において、それでもなお自らの自立した意志をもとに自己超克を続ける超人であり続けること。そしてそのような生を肯定すること。たとえ、それが無限に繰り返されるとしても。
これが「ツァラトゥストラはかく語った」の中心的思想であり、ニーチェ哲学の1つの到達点でもあります。
ツァラトゥストラは「いまここ」思想の源流
「今日という一日を未来永劫、永遠に繰り返したとしても自分の人生を肯定できるか?」
これは実存主義だけでなく、アドラー心理学やマインドフルネスに始まる現代のブームの1つ「いまここ」という概念に共通する考え方です。時代的には源流といっていいかもしれません。「ツァラトゥストラはこう言った」 が出版されたのは19世紀末。当時、この考え方はあまりに非常識であり、非常識どころか不道徳でもありました(そのため本書の大きなテーマの1つに善悪の矛盾があります)。
現代ようやく社会がニーチェに追いついたようで、未来や過去にとらわれず現在に集中して生きるこのような考え方は一般的になり、激動の時代においてその必要性は高まるばかりです。
同じくドイツの哲人であり、実存主義のパイオニアでもあるショーペンハウアーの「意志と表象としての世界」も私の生きる指針として強烈に機能してくれているのですが、「ツァラトゥストラはこう言った」の方はより現実的で俗世における葛藤や疑問に回答してくれるので、実用的な一冊として愛読しています。
なかなかの長編ですが、人生のあらゆる面で生きる思想が詰め込まれているので、ご興味あればお手にとってみてください。

▼また、本書について動画による解説もありますので、ながら聴きなどこちらをご覧ください。
貴下の従順なる下僕 松崎より
 jMatsuzaki TaskChute Cloud開発者ブログ
jMatsuzaki TaskChute Cloud開発者ブログ